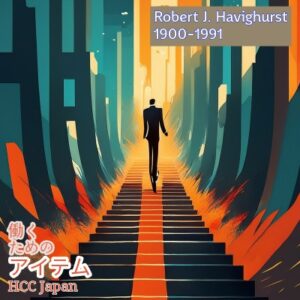キャリア理論05|エリクソンの理論.5
キャリアに
アイディアを
働くためのアイテム
「働くためのアイテム」を探究することで、変化の激しい社会の中で、私たち一人ひとりが、主体的に自身の希望や適性、そして能力を生涯にわたって発揮できるます。私たちの未来をより豊かにするために、キャリアにアイディアというエッセンスを加え、働くためのアイテムを一緒に探っていきましょう。
挑戦し続ける力
自分だけの価値観で、豊かな人生をデザインする。
もっと自分らしく生きたい!そう思える社会、そしてより多くの人々が自分自身の人生と向き合い、より豊かな人生を送るきっかけつくりをHCCジャパンはお手伝いします。

キャリア理論05|エリクソンの理論.5(エリクソンの理論から見える中高年期の展望)
これまでエリクソンの心理社会的発達理論を通じて、キャリアが単なる職業選択ではなく、生涯にわたる自己形成のプロセスであることを確認してきました。最終章となる今回は、現代社会でその重要性が高まっている中高年期(成人期から老年期)に焦点を当て、エリクソンの理論がこの時期のキャリアにどのような洞察を与えるのかを深く探っていきます。
中高年期の発達課題:自己と社会への貢献
エリクソンは、人生の各段階に固有の「心理社会的危機」が存在するとし、それを乗り越えることで「基本的強さ」を獲得し、自己が成熟すると考えました。中高年期に差し掛かると、私たちは主に以下の二つの発達課題に直面します。
成人期<壮年期>:世代性 vs. 停滞性
およそ40歳から60歳頃に訪れるこの時期の中心的課題は、「世代性(Generativity)」です。これは、実子の育成に限らず、仕事や地域活動を通じて社会に貢献し、価値を創出しようとする意欲を指します。世代性が達成されると、自己の存在意義や充実感が高まり、社会とのつながりも深まります。一方、世代性が十分に発揮されない場合、停滞性(Stagnation)が現れます。自己中心的になり、他者や社会への関心が薄れることで、閉塞感や無力感を感じやすくなります。キャリアにおいては、仕事のマンネリ化、目標の喪失、モチベーションの低下などとして現れることもあります。
キャリアにおける世代性の具体例:
- 後進の育成:部下や若手社員への指導・育成を通じて、知識や経験を継承する。
- 価値創出:新規プロジェクトの推進や、社会的課題への取り組みを通じて、組織や地域に貢献する。
- 自己実現:仕事を通じて「社会に役立っている」という実感を得ることで、深い満足感を得る。
老年期:統合性 vs. 絶望
およそ60歳以降に訪れる人生の最終段階では、これまでの人生(仕事、家庭、人間関係、挑戦と失敗)を振り返り、その歩みを肯定的に受け入れる「統合性(Ego Integrity)」の達成が課題となります。成功だけでなく、困難や葛藤も含めて、自らの人生に一貫した意味を見出すことができれば、穏やかな充足感と精神的安定が得られます。この統合感は、単なる満足ではなく、深い知恵(wisdom)として現れます。次世代への助言や社会への価値の継承にもつながります。一方、過去の選択に対する後悔や未達成感が強い場合、絶望(Despair)が生じます。「もっとこうしていれば」といった思いに囚われることで、心理的な安定を損ない、社会との関わりも希薄になりがちです。
キャリアにおける統合性の具体例:
- キャリアの振り返りと納得感の獲得:定年退職を迎える際、「自分はこの仕事を通じて多くの人に貢献できた」「困難もあったが、乗り越えた経験が自分を成長させた」と感じる。
- 知恵の伝承:退職後に若手社員向けのメンターとして活動し、自身の経験を語り継ぐ。
- セカンドキャリアでの社会貢献:専門職を退いた後、地域のNPOやボランティア活動に参加し、社会的な価値を生み出す。
- 自伝や回顧録の執筆:自分の職業人生を振り返り、書籍やブログで発信する。
- 家族や仲間との語らいを通じた再評価:家族や旧友と過去の仕事や人生について語り合い、「あの時の選択は間違っていなかった」と再認識する。
これらの行動は、老年期におけるキャリアの「終わり」ではなく、「統合と継承」の段階としての意味を持ちます。統合性が育まれることで、人生の最終章においても安心感・充足感・社会とのつながりを保ち続けることが可能になります。
中年期の危機(ミッドライフ・クライシス)とキャリアの再構築
エリクソンが提唱する「世代性 vs. 停滞性」という発達課題は、しばしば「中年期の危機(ミッドライフ・クライシス)」と関連付けられます。これは、40代から50代にかけて、これまでの人生やキャリアを深く見つめ直し、このままで良いのか、本当にやりたかったことは何かと自問自答する時期です。
この危機は、単なるネガティブなものではなく、キャリアを再構築し、人生の後半戦をより充実させるための重要な機会と捉えることができます。
- キャリアの棚卸しと再評価:これまでのキャリアで培ったスキル、経験、ネットワーク、そして本当に大切にしたい価値観を改めて棚卸しし、再評価することで、今後の方向性が明確になります。また、「何をしてきたか」だけでなく、「何を大切にしてきたか」「何をこれから活かしたいか」に焦点を当てることが重要です。
- 「世代性」の追求:停滞感を乗り越えるためには、「自分は何を社会に残せるか」「誰かの役に立てるか」という世代性の視点を持つことが有効です。具体的には、マネジメント職への転身、NPO活動への参加、自身の専門性を活かした独立・副業などが考えられます。社会とのつながりを再構築することは、キャリアに新たな意味と活力が生まれます。
- 新たな学習と挑戦:環境の変化やテクノロジーの進化に対応するため、新しい知識やスキルの習得に意欲的に取り組むことも、中年期の停滞を打ち破る鍵となります。リスキリング、学び直しを通じて、これまでの経験と新たな知識を融合させることで、新しいキャリアの可能性が拓けることも少なくありません。
中年期の危機を乗り越え、世代性を発揮することは、キャリアを停滞させることなく、より深い充足感と社会的意義へと導く重要なプロセスです。エリクソンの理論は、この時期の揺らぎを「自己の再構築」として捉える視点を提供してくれます。
転職を考えている社会人の皆様に
成人期中期以降の社会人の皆さんにとって、キャリアの再評価や転職を考える際は、エリクソンの「世代性」や「統合性」といった発達課題の視点を取り入れることが非常に有効です。これらの視点は、単なる職務変更ではなく、人生の意味を再構築するキャリア選択を促してくれます。
「世代性」の視点から:もし現在の仕事に停滞感や物足りなさを感じているのであれば、次のような問いを立ててみてください。
- 「今の仕事で、私は社会や次世代に何を貢献できているだろうか?」
- 「私の経験やスキルは、もっと他の場所で活かせるのではないか?」
このような問いは、キャリアの本質的な価値を見直すきっかけになります。単なる役割や待遇の変化ではなく、「より深い意味での生産性」を求めてキャリアチェンジを検討することは、新たな充実感と活力を生み出します。
具体的には:
- 管理職への挑戦:人材育成や組織運営を通じて、次世代への貢献を果たす。
- 異分野への転身:これまでのスキルを新しい領域で応用し、社会的価値を創出する。
- 社会貢献度の高い仕事への移行:NPOや地域活動など、公共性の高い分野での活躍する。
単なる役割や待遇の変化だけでなく、「より深い意味での生産性」を求めてキャリアチェンジを検討することは、新たな充実感と活力を生み出すでしょう。管理職への挑戦、異なる分野でのスキル応用、社会貢献度の高い仕事への移行などが考えられます。
「統合性」の視点から:人生の後半期に差し掛かっている方にとっては、これまでのキャリアを振り返り、次のような問いを立てることが重要です。
- 「自分はどんな仕事人生を送ってきたか?」
- 「このままで後悔しないか?」
この問いは、セカンドキャリアの方向性を見定める上での指針となります。引退後の自分が何に価値を見出し、どのように生きていきたいかを考えることで、後悔のない選択につながります。そして、この視点は、単に収入を得るためだけでなく、生きがいや自己実現の場としての仕事を探すことを促します。統合性の視点を持つことで、キャリアは「終わり」ではなく、「意味づけと継承」の段階へと移行します。
Take-Home Message
エリクソンの心理社会的発達理論は、中高年期におけるキャリアの意味を再定義する、力強い視点を提供してくれます。
この時期のキャリアは、単に役割や職務をこなすことにとどまらず、社会や次世代への貢献である世代性と、人生の意味の再構築である統合性という、深い心理的課題と結びついています。
- 世代性は、これまで培ってきた知識や経験を他者に還元することで、キャリアに新たな意義と活力をもたらします。
- 統合性は、仕事人生を振り返り、そのすべてに納得と意味を見出すことで、精神的な成熟と安定を育みます。
もし今、ミッドライフ・クライシスのような揺らぎを感じているなら、それはキャリアの再構築と自己理解の深化を促す重要な転機です。
転職やキャリアチェンジを考える際には、ライフステージに応じた発達課題の視点を取り入れることで、より本質的で後悔のない選択が可能になります。
キャリアとは、「働くこと」だけでなく、「生きること」と深く結びついています。
中高年期は、これまでの経験を最大限に活かし、社会と自己の両方に価値を還元しながら、あなたの人生の物語を完成させていく成熟のステージなのです。
キャリアとは、「働くこと」だけではなく、「生きること」と深く結びついています。中高年期は、これまでの経験を最大限に活かし、社会と自己の両方に価値を還元しながら、あなたの「人生の物語」を完成させていく、まさに成熟のステージです。
エリクソンの理論を学んで
エリクソンの心理社会的発達理論は、私たちのキャリアに対する見方を大きく広げてくれます。これまで見てきたように、キャリアは単なる職務経歴や職業選択の「点」ではなく、人生の始まりから終わりまで続く「線」、さらには各段階が有機的に繋がり影響し合う「円環」として捉える視点を与えてくれています。
エリクソンは、人生の各段階で誰もが直面する固有の心理社会的危機と、それを乗り越えることで得られる基本的強さを明らかにしました。乳幼児期に培われる信頼や自律性、青年期の核となるアイデンティティ(同一性)、成人前期の親密性、成人期中期の世代性、そして老年期の統合性。これらの発達課題は、キャリアの選択、継続、転換、そして最終的な満足度に深く関わっています。
つまり、エリクソンの理論から見えてくるのは、キャリアとは自己形成の延長線上にある生き方そのものであるということです。仕事を通じて私たちは自己を表現し、他者と関わり、社会に貢献し、そして成長していきます。キャリアの悩みや迷いは、一見すると困難に見えるかもしれません。しかし、エリクソンの理論を理解することで、これらを自己成長の機会として前向きに捉える力を得ることができます。
どのライフステージにおいても、キャリアは「自分らしく生きる」ための大切な手段であり、あなたの人生に意味と充足感をもたらすプロセスです。この視点を持つことで、私たちは変化の多い現代社会においても、しなやかに、そして主体的にキャリアを築いていきたいと願ってやみません。
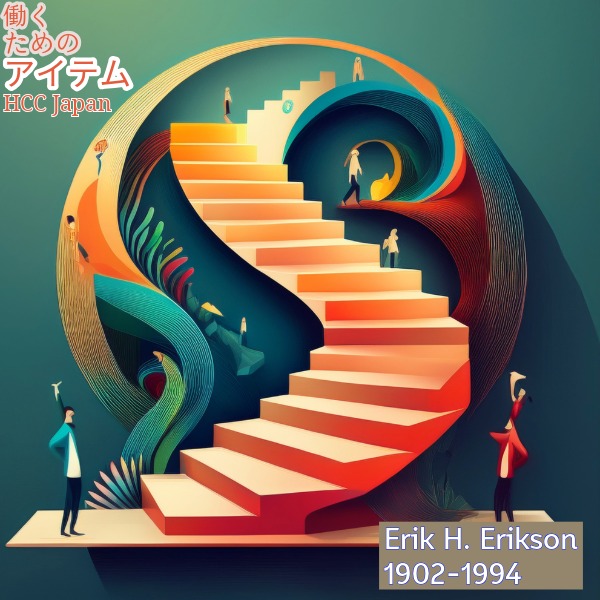
この記事を書いた人
プロフィール
HCC Japan LLC
CEO
Tokyo University Of Agriculture in Faculty of Bioindustry
Eli Lilly Japan K.K.
Sales & Marketing
Sales Manager
Sales Operator
Waseda University in School of Human Sciences (e-school)
Human Informatics and Cognitive Sciences
Waseda University Senior High School
Teaching Assistant (Information Technology)
Waseda University School of Human Sciences
Teaching Assistant (Collaborative Learning and the Learning Sciences)
会社概要
-COMPANY PROFILE-
\ようこそ/
HCCジャパンの提案
歴史は人がつくる
人は歴史をつくる
いらすと
すてーしょん
"いらすとすてーしょん"は独自のタッチで描いた
フリーイラストポートレートと歴史の停車場の提供を
通じて世代を繋ぐ遺産として、そして未来への脈動を
提案します