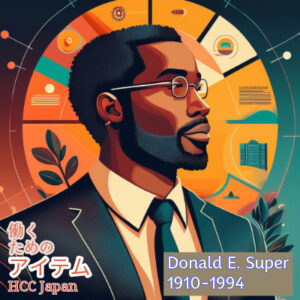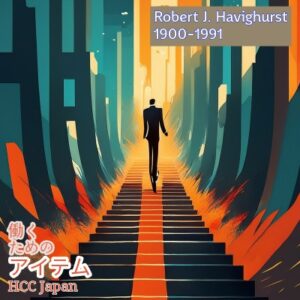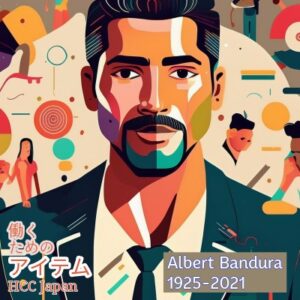キャリア理論06|バンデューラの理論.1
キャリアに
アイディアを
働くためのアイテム
「働くためのアイテム」を探究することで、変化の激しい社会の中で、私たち一人ひとりが、主体的に自身の希望や適性、そして能力を生涯にわたって発揮できるます。私たちの未来をより豊かにするために、キャリアにアイディアというエッセンスを加え、働くためのアイテムを一緒に探っていきましょう。
挑戦し続ける力
自分だけの価値観で、豊かな人生をデザインする。
もっと自分らしく生きたい!そう思える社会、そしてより多くの人々が自分自身の人生と向き合い、より豊かな人生を送るきっかけつくりをHCCジャパンはお手伝いします。

キャリア理論06|バンデューラの理論.1(概要と自己効力感とは?)
バンデューラって?
アルバート・バンデューラ(Albert Bandura, 1925-2021)は、カナダ生まれの心理学者で、社会的学習理論(Social Learning Theory)を提唱したことで知られています。バンデューラは、人間の行動が「観察学習」によって形成されることを明らかにし、後にこの理論を発展させて自己効力感(Self-Efficacy)という概念を導入しました。
バンデューラの理論は、「学習」や「スキル獲得」といった外的な側面だけでなく、「自分にはできる」という内なる信念が、行動の選択や持続にどれほど影響するかを示した点で画期的です。この信念こそが、不確実性に満ちた現代のキャリア形成において極めて重要な役割を果たします。
自己効力感(Self-Efficacy)とは?
自己効力感とは、「ある状況で必要な行動をうまく遂行できるという、自分の能力に対する確信」を指します。簡単に言えば、「自分ならできる」という心のエンジンです。キャリア形成において、この信念の有無は決定的です。
| 特徴 | 高い自己効力感を持つ人 | 低い自己効力感を持つ人 |
| 挑戦 | 困難な課題にも積極的に挑戦し、目標を高く設定する。 | 挑戦を避け、失敗を恐れ、目標を低く設定しがち。 |
| 粘り強さ | 失敗しても原因を分析し、粘り強く取り組む。 | 失敗を能力不足とみなし、早々に諦めやすくなる。 |
参考
| 高い自己効力感 | 低い自己効力感 | |
|---|---|---|
| 例1) 昇進の打診 | 「新しい役割は大変そうだけど、学べばできるはず。挑戦してみよう!」 → 新しいスキルを積極的に学び、リーダーシップを発揮する。 | 「自分には無理だ。失敗したらどうしよう…」 → 打診を断り、現状維持を選択。結果、成長の機会を逃す。 |
| 例2) 英語プレゼン | 「完璧じゃなくても、準備すればできる!」 → 英語スキルを磨き、国際プロジェクトに参加。キャリアの幅が広がる。 | 「英語は苦手だから、誰かに代わってもらおう…」 → チャンスを逃し、グローバル案件から外れる。 |
| 例3) DXプロジェクト | 「ITは専門外だけど、学べば対応できる」 → 新しいスキルを習得し、社内での価値を高める。 | 「自分には無理。若い人に任せよう」 → キャリアが停滞し、役割縮小のリスク。 |
自己効力感とキャリア形成の関係
キャリアの意思決定や行動は、能力そのものよりも、「自分にできると思えるかどうか」に大きく左右されます。この信念が、キャリアのあらゆる分岐点での行動を決定づけます。
- 職業選択:新しい分野に挑戦するか、安全な選択をするか
- キャリア転換:未知の領域に飛び込む勇気を持てるか
- スキル習得:学び続けるモチベーションを維持できるか
自己効力感が高い人は、キャリアの選択肢を広げ、困難を乗り越える力を発揮します。一方、自己効力感が低いと、可能性を自ら狭めてしまうことになります。
他のキャリア理論との違いと補完関係
バンデューラの理論は、「行動を起こす力の源泉」に焦点を当てています。つまり、他の理論(スーパー、エリクソン、ハヴィガースト)が示す「やるべきこと」や「なぜやるのか」という課題に対して、「やれると思えるか」という視点を加えることで、キャリア理論をより実践的で力強いものにします。
スーパーの理論:キャリア発達を「役割」や「ライフスパン」で捉える。
スーパー理論では「30代はキャリアの確立期」と表現されていますが、自己効力感が低い人は「転職したいけど自信がない」と動けません。一方で、自己効力感が高い人は「学べばできる」と考え、積極的にキャリアチェンジに挑戦する姿勢があります。
参考
キャリア理論04|スーパーの理論.1
エリクソンの理論:内面的な心理社会的課題に焦点を当てる。
例えば、エリクソンの理論のおける中年期に「後進育成」という課題があります。このとき、自己効力感が低い管理職は「自分が関わっても聴いてくれない」と思い、部下育成を回避する傾向があります。一方で、自己効力感が高い管理職は「自分が関われば必ず良い方向に向かう」と考え、メンタリングを積極的に実施する姿勢が伺えます。
参考
キャリア理論05|エリクソンの理論.1
ハヴィガーストの理論:ライフステージごとの「発達課題」を提示する。
例えば、ハヴィガーストの理論のおける壮年期の課題には「職業に就く」や「家庭を築く」があります。このとき、自己効力感が低い人は「自分に合う仕事はない」と就職活動に積極的に取り組めない傾向があります。一方で、自己効力感が高い人は「努力すれば見つかる」と積極的に行動し課題を達成します。
参考
キャリア理論05|ハヴィガーストの理論.1
Take-Home Message
キャリアを切り拓くのは、スキルや知識だけではありません。「自分にはできる」という信念(自己効力感)こそが、キャリアを動かすエンジンです。この信念があるかどうかで、昇進の打診を受けるか断るか、DXプロジェクトに挑戦するか傍観するかなど、キャリアの分岐点での選択が大きく変わります。もし今、「新しい役割に挑戦する自信がない」や「一歩踏み出せない」など、迷いを感じているなら、それは能力不足ではなく、自己効力感の問題かもしれません。そこで次回は、「キャリア理論06|バンデューラの理論.2(自己効力感を形成する4つの要因)」を通じて、自己効力感をどう育てるか、その具体的なメカニズムを深掘りしていきます。
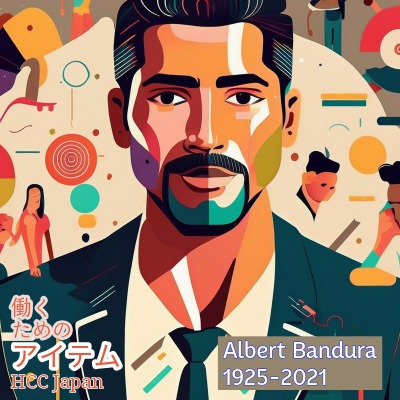
この記事を書いた人
プロフィール
HCC Japan LLC
CEO
Waseda University in School of Human Sciences (e-school)
Human Informatics and Cognitive Sciences
Tokyo University Of Agriculture in Faculty of Bioindustry
Eli Lilly Japan K.K.
Sales & Marketing
Sales Manager
Sales Operator
Waseda University Senior High School
Teaching Assistant (Information Technology)
Waseda University School of Human Sciences
Teaching Assistant (Collaborative Learning and the Learning Sciences)
会社概要
-COMPANY PROFILE-
\ようこそ/
HCCジャパンの提案
歴史は人がつくる
人は歴史をつくる
いらすと
すてーしょん
"いらすとすてーしょん"は独自のタッチで描いた
フリーイラストポートレートと歴史の停車場の提供を
通じて世代を繋ぐ遺産として、そして未来への脈動を
提案します