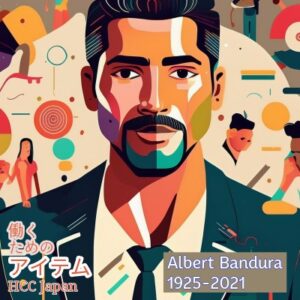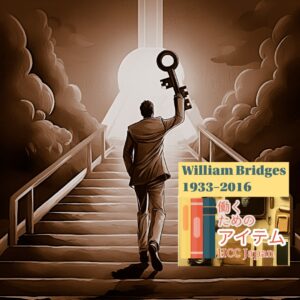キャリア理論06|バンデューラの理論.4
キャリアに
アイディアを
働くためのアイテム
「働くためのアイテム」を探究することで、変化の激しい社会の中で、私たち一人ひとりが、主体的に自身の希望や適性、そして能力を生涯にわたって発揮できるます。私たちの未来をより豊かにするために、キャリアにアイディアというエッセンスを加え、働くためのアイテムを一緒に探っていきましょう。
挑戦し続ける力
自分だけの価値観で、豊かな人生をデザインする。
もっと自分らしく生きたい!そう思える社会、そしてより多くの人々が自分自身の人生と向き合い、より豊かな人生を送るきっかけつくりをHCCジャパンはお手伝いします。

キャリア理論06|バンデューラの理論.4(自己効力感を高めるための戦略とキャリア支援)
前回の振り返り
前回(バンデューラの理論.3)では、自己効力感がキャリアに与える3つの決定的な影響として、① キャリア選択の幅を広げる、② 行動の持続力を左右する、③ キャリア満足度と成長感に影響するをご紹介しました。そして、不確実な令和時代において、自己効力感が「羅針盤」であり「エンジン」である理由を確認しました。最終回となる今回は、この重要な自己効力感をどう高めるかを、個人・組織・キャリア支援の3つの視点から具体的に見ていきます。
個人ができること:日常で自己効力感を育てる習慣
自己効力感は、生まれつきのものではありません。バンデューラが提唱する4つの要因を、日常の中で意識的に積み重ねることで強化できます。
| 要因 | ポイント | 実践例 |
| ① 達成経験 | 大きな挑戦よりも、日常の**「小さな勝ち」**を意識する。 | 1日1つ、新しい業務に挑戦する。オンライン講座を10分間受講するなど、具体的な成功体験を記録する。 |
| ② 代理経験 | 自分と似た立場で成功している人を観察する。 | 社内の先輩や同僚の成功事例を積極的に聞く。コミュニティでロールモデルのストーリーからヒントを得る。 |
| ③ 言語的説得 | ポジティブな言葉を自分に、そして他者からも得る。 | 自分に「やればできる」と声をかけるセルフトークを行う。信頼できる人に相談し、励ましを受ける。 |
| ④ 生理的・情緒的状態 | ストレスや疲労は**「できる感覚」**を奪うことを理解する。 | 睡眠・運動・食事のリズムを整える。プレゼン前に深呼吸で緊張を和らげるなど、心身のコンディションを整える。 |
組織ができること:社員の自己効力感を支える仕組み
組織が意図的に環境を整備することで、社員一人ひとりの「挑戦する力」を引き出すことができます。
成功体験を積ませる仕事設計: 小さなプロジェクトを任せ、達成感を得られる環境をつくる(ストレッチアサインメント)。
ロールモデルの可視化: 社内でキャリア成功事例を共有する**「キャリアストーリーセッション」**などを定期開催する。
フィードバック文化の醸成: 上司が「できていない点」ではなく**「できている点」**や「成長の兆し」を具体的に伝える習慣を持つ(言語的説得の強化)。
メンタルヘルス支援: ストレスマネジメント研修や相談窓口を整備し、心身のベースラインを維持する。
キャリアカウンセリングでの活用
キャリア支援の現場では、自己効力感を「診断」し「意図的に高める」ためのアプローチがとられます。
行動計画の小ステップ化: 最終目標から逆算し、「まずは1週間でできること」といった小さなステップに落とし込み、初期の成功体験を確実に積ませる。
自己効力感のアセスメント: 質問紙や面談で、どの領域(例:転職、スキル習得、昇進など)で自己効力感が低いかを把握する。
成功体験の棚卸し: 過去に困難を**「どう乗り越えたか」を深く振り返り、クライアント自身の強みや成功パターン**を再認識させる(達成経験の言語化)。
Take-Home Message
自己効力感は、偶然に任せるものではありません。
「小さな成功」「ロールモデル」「励ましの言葉」「心身のコンディション」――この4つを意識的に積み重ねることで、キャリアのエンジンは確実に強化されます。
令和時代のキャリアは、「正解がない世界で、自分で選び続ける」ことが求められます。そのとき、最も信頼できる“よりどころ”は、スキルや肩書きではなく、「自分ならできる」という信念=自己効力感です。
キャリア理論07では、アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)の社会的学習理論、特に自己効力感(Self-Efficacy)に焦点を当て、4回にわたって解説しました。自己効力感とは、「ある状況で必要な行動をうまく遂行できるという、自分の能力に対する確信」です。簡単に言えば、「自分ならできる」という信念です。
この信念は、キャリアの分岐点での意思決定、行動の持続力、そしてキャリア満足度を大きく左右します。では、4回分のポイントを総括し、令和時代を生き抜くキャリア戦略としての自己効力感を整理します。
第1回:自己効力感とは何か?
- 自己効力感は、キャリアの「羅針盤」であり「エンジン」
- 高い自己効力感を持つ人は、挑戦を恐れず、失敗しても粘り強く取り組む
- 低い自己効力感を持つ人は、挑戦を避け、現状維持を選びやすい
- 他のキャリア理論との違い:
スーパーやハヴィガーストが「何をすべきか」を示すのに対し、バンデューラは「やれると思えるか」という行動の起点に焦点を当てる
キャリア理論06|バンデューラの理論.1
第2回:自己効力感を育てる4つの要因
- 達成経験(Mastery Experiences)
小さな成功体験を積み重ねることが最も強力な要因 - 代理経験(Vicarious Experiences)
ロールモデルの成功を見て「自分にもできる」と思える - 言語的説得(Verbal Persuasion)
信頼できる人からの励ましや具体的なフィードバック - 生理的・情緒的状態(Physiological & Emotional States)
心身のコンディションが「できる感覚」に影響
キャリア理論06|バンデューラの理論.2
第3回:自己効力感がキャリアに与える3つの影響
- キャリア選択の幅を広げる
→ 昇進、転職、リスキリングなどの分岐点で挑戦できるかどうか - 行動の持続力を左右する
→ DXプロジェクトやスキル習得で「やり抜く力」を支える - キャリア満足度と成長感に影響する
→ 挑戦と達成の積み重ねが、キャリアを「物語」に変える
令和時代の背景:
DX・AI、ジョブ型雇用、副業解禁、人生100年時代
「正解がない世界で、自分で選び続ける」ために、最も信頼できるよりどころは、スキルや肩書きではなく、「自分ならできる」という信念
キャリア理論06|バンデューラの理論.3
第4回:自己効力感を高めるための戦略
- 個人
小さな成功を積む、ロールモデルを見つける、ポジティブなセルフトーク、心身のケア - 組織
成功体験を積ませる仕事設計、キャリア事例の共有、フィードバック文化、メンタルヘルス支援 - キャリア支援
自己効力感のアセスメント、成功体験の棚卸し、小ステップの行動計画
バンデューラの理論を通じて、皆様がその道をより豊かに、より納得感を持って歩んでいけることを心から願ってやみません。
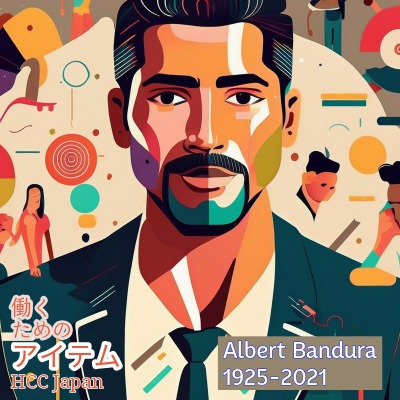
この記事を書いた人
プロフィール
HCC Japan LLC
CEO
Waseda University in School of Human Sciences (e-school)
Human Informatics and Cognitive Sciences
Tokyo University Of Agriculture in Faculty of Bioindustry
Eli Lilly Japan K.K.
Sales & Marketing
Sales Manager
Sales Operator
Waseda University Senior High School
Teaching Assistant (Information Technology)
Waseda University School of Human Sciences
Teaching Assistant (Collaborative Learning and the Learning Sciences)
会社概要
-COMPANY PROFILE-
\ようこそ/
HCCジャパンの提案
歴史は人がつくる
人は歴史をつくる
いらすと
すてーしょん
"いらすとすてーしょん"は独自のタッチで描いた
フリーイラストポートレートと歴史の停車場の提供を
通じて世代を繋ぐ遺産として、そして未来への脈動を
提案します